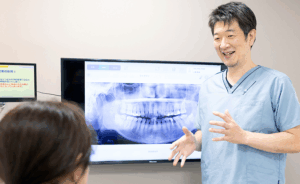こんにちは、学芸大学の歯医者 碑文谷さくら通り歯科 院長の太田です。
「朝の口臭が気になる」「マスクを外す機会が増えて不安」「家族や同僚に指摘された」――口臭はデリケートなお悩みですが、原因の8割以上はお口の中にあります。歯科医師として26年の臨床から、誰にでも起こる“生理的口臭”と、治療が必要な“病的口臭”を見分け、確実に改善へ導くための手順をわかりやすく解説します。初診の流れは初めての方へをご確認ください。
目次
口臭の正体:VSC(揮発性硫黄化合物)とその発生源
強い口臭の主犯は、嫌気性菌がタンパク質を分解して作る揮発性硫黄化合物(VSC)です。代表は硫化水素・メチルメルカプタン・ジメチルサルファイド。発生源は主に舌表面(舌苔)、歯周ポケット、むし歯の穴、適合不良の詰め物・被せ物周辺など。これらはバイオフィルム(細菌の膜)に守られているため、うがいだけでは除去しきれません。だからこそ、歯科での物理的除去と家庭の正しい道具選びが重要になります。
“生理的”と“病的”を見分けるセルフチェック
朝起きた直後、空腹時、緊張時は唾液が減り一時的に口臭が強くなるのが普通です。これは水分補給・朝食・歯磨きで概ね改善します。一方、一日中続く、出血を伴う、痛みや腫れを伴う場合は“病的口臭”の可能性が高いサイン。コップやスプーンに息を吹きかける方法は主観に左右されるため、家族の協力や、当院での数値化(口臭測定器)・歯周検査を併用して客観評価します。
主な原因① 歯周病・歯肉炎:出血と炎症がにおいを増幅
歯周病では、ポケット内部の嫌気性菌がVSCを産生し、出血(BOP)が栄養源となってにおいが増幅します。歯ぐきの腫れ、歯ブラシでの出血、歯が浮いた感じ、口臭の悪化がセットで起こることが多いです。対策の王道は、スケーリング・ルートプレーニングによるバイオフィルムと歯石の徹底除去と、力学的要因(強い噛みしめなど)の同時コントロール。炎症の火元から治すことが肝心です。詳しくは歯周病治療をご覧ください。
主な原因② 舌苔・ドライマウス・口呼吸:舌と唾液のケア
舌の表面は乳頭が密集し、汚れがたまりやすい構造です。白〜黄褐色の舌苔が厚いと口臭が強くなります。対策は、専用の舌ブラシで奥から手前へ“軽く”なでること。力を入れすぎると傷や味覚障害の原因になるため注意が必要です。
また、ドライマウス(口腔乾燥)は細菌の代謝を活発化させます。口呼吸、喫煙、加齢、服薬(抗うつ薬・抗ヒスタミン薬など)も乾燥を助長。唾液腺マッサージやこまめな水分補給、キシリトールガム、加湿、鼻呼吸への切り替えを提案します。口呼吸の背景に歯並びや鼻疾患がある場合は、矯正治療や耳鼻科との連携も検討します。
主な原因③ むし歯・詰め物の段差・噛み合わせの不具合
深いむし歯や、適合不良の詰め物・被せ物の隙間は、食残や細菌が停滞しやすく、強いにおいの温床です。歯の破折(とくに歯根破折)も独特の口臭を伴うことがあります。これらはセルフケアだけでは改善しないため、虫歯治療や、封鎖性と清掃性を両立させるやり直しの少ない治療で構造から見直します。親知らず周囲の炎症や食片圧入が原因のこともあり、その際は口腔外科で抜歯・洗浄を検討します。
食習慣・生活習慣:においを強くする日々のクセ
コーヒー・紅茶・アルコール・ニンニク・ネギ・スパイスは一過性の口臭を強めます。間食の頻度、糖質のダラダラ摂取はむし歯リスクを上げ、結果的に口臭へつながります。喫煙は乾燥と血流悪化のダブルパンチ。まずは“頻度”と“タイミング”を整え、寝る前2時間は飲食を控えるだけでも改善を実感しやすくなります。生活改善の具体策は予防歯科で個別に設計します。
当院の診断プロセス:原因の“見える化”と治療の打ち手
初診では、問診・口腔写真・歯周検査(BOP、ポケット、動揺度)・舌苔評価を行い、必要に応じてレントゲン・CTで歯根破折や隠れたむし歯を確認します。口臭は数値(VSC)と所見を時系列で見える化し、原因を特定したうえで治療へ。
- 炎症型:スケーリング、ルートプレーニング、噛み合わせの是正(歯周病治療)。
- 舌苔・乾燥型:舌清掃指導、保湿、鼻呼吸トレーニング、生活リズム調整(予防歯科)。
- 構造問題型:むし歯・不適合補綴の是正、親知らず対応(虫歯治療/やり直しの少ない治療/口腔外科)。
改善後は、再発防止のためにメインテナンスへ移行し、数値の推移をチェックします。費用の目安は価格表をご参照ください。

今日からできるホームケア:最短で効く道具と手順
“やることが多すぎて続かない”を避けるために、まずは3点セットから。
- フロス:毎晩。接触がきつい部位はワックスタイプ、広い部位はテープ型。
- 歯間ブラシ:サイズ選定が命。入る最大サイズで無理なく水平に1〜2往復。
- 舌ブラシ:朝1回、奥から手前に軽く3〜5ストローク。やり過ぎ禁止。
順番は「フロス → 歯間ブラシ → 舌ブラシ → 歯ブラシ」。仕上げの歯ブラシはペースト量を控えめにし、泡でごまかさないのがコツです。
知覚過敏がある方は、カリウム塩・硝酸カリウム配合のペーストを先行使用。口呼吸が疑われる場合は、就寝前に鼻呼吸トレーニングや加湿を。具体的なツールと当て方は、来院時にお口に合わせてカスタマイズします(詳細は予防歯科)。
再発させない仕組み:メインテナンスと費用の目安
口臭は“治す”だけでなく“維持する”ことが大切。炎症が落ち着いた後も、3か月を基準にプロケアでバイオフィルムをリセットし、舌苔や乾燥の傾向、生活リズムの変化を確認します。喫煙・糖尿病・強い歯ぎしり・矯正中などリスクが高い方は2か月間隔を推奨。安定していれば4〜6か月へ延長可能です。通院の導線はメインテナンスに記載しています。
費用は処置内容で異なります。まずは検査・クリーニングから始め、必要に応じて歯周基本治療、補綴の再設計、親知らずの対応などを段階的に行います。概算は価格表をご確認ください。治療後は症例紹介のように“ビフォー・アフター”を写真で共有し、モチベーション維持をお手伝いします。
まとめ:においの不安を“構造的に”解決する
口臭の多くは、お口の中の問題を整理すれば改善できます。歯周病の火消し、舌と唾液のケア、むし歯・補綴の構造改善、そして生活習慣の最適化。この4本柱を、検査に基づきオーダーメイドで実行するのが最短ルートです。学芸大学・碑文谷エリアで“においの不安から解放されたい”方は、まずは診査で現在地を把握し、あなたに合うプランを一緒に作りましょう。初診手順は初めての方へ、原因別の詳しいページは歯周病治療・虫歯治療・予防歯科、再発防止はメインテナンスをご参照ください。費用は価格表で事前確認いただけます。
碑文谷さくら通り歯科/学芸大学駅 徒歩圏
院長 太田 彰人
日本歯周病学会 認定医/日本顎咬合学会 認定医/かみ合わせ認定医/厚生労働省認定研修指導医/歯学博士