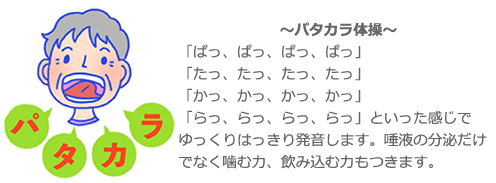こんにちは、学芸大学の歯医者、碑文谷さくら通り歯科 院長の太田です。
ネット広告や街中の看板等でインビザラインと目にしたことがある方は多いのでないでしょうか?
今回はインビザラインについて書いていこうと思います。
インビザラインとは?
インビザラインは、皆さんが矯正でイメージされる金具やワイヤーを使用せずに、自分でいつでも取り外しが出来る透明で目立ちにくいマウスピース型の装置を活用して歯並びを治すという矯正治療です。
従来のワイヤーを使用した矯正治療は目立つのが難点でしたが、インビザラインは透明のマウスピース型の装置を活用するため目立ちにくく、マスク着用している昨今では、尚の事矯正治療をしていることに気付かれにくいのが特徴です。
使い方は非常に簡単で、薄くて透明なマウスピースを一日20時間以上装着し、1~2週間ごとに型が若干異なる新しいマウスピースに交換していきます。新しいマウスピースを使うことで歯を徐々に動かし、歯並びを整えていきます。
使用するマウスピースは最初の段階で全てまとめて作りますので、頻繁にかかりつけの歯科医院に通い、歯型を取って作ってを繰りかえす、、、という必要はありません。
インビザラインは世界100カ国以上の国々で提供され、これまでに1700万人を超える患者さまが治療を受けています。治療効果も実証されている矯正治療です。

インビザラインの歴史
自分や子どもの歯並びが気になるけど、なかなか始められない・・・という方は多くいらしゃいます。
その最大の要因となっていたのは「目立つワイヤー装置が嫌、、、」「ワイヤー矯正はむし歯になりやすいと聞いたことがある、、、」といったものです。
そんな方用に歯の裏側にワイヤーをつけて矯正治療をする舌側矯正というのが、ずいぶん前に開発されました。非常に良い方法だったのですが、治療費が通常のワイヤー矯正より高いということもあり、一般的にはハードルの高い治療方法となっていました。
そんな中、インビザラインはアメリカで1997年に開発され、2005年から日本に導入されました。 ワイヤーを使わずに透明で薄いマウスピースを使うという画期的な方法で、世界中の注目を集めました。当初歯科医師の中でも賛否両論がありましたが、研究や改良を重ねていった結果、確実な効果が表れています。

新しい矯正治療方法にも関わらず、インビザラインで矯正治療を受けた方がすでに世界で1700万人を突破しており、当院でもインビザラインを希望される患者様が毎月増えています。
これは明確に効果が現れており、医学的に世界中の歯科医師から信頼を得られている治療法だという証拠です。
現在では、矯正治療の新しいスタンダードになりつつあります。
透明なマウスピースなので目立ちにくく、食事をする際は自分で外すことが出来るという最大のメリットがあり、そして何より矯正治療としても効果が実証されているインビザライン。
学芸大学にある碑文谷さくら通り歯科では無料相談も行っておりますので、もしご興味があればご連絡を頂ければと思います。
碑文谷さくら通り歯科
院長 太田彰人
日本歯周病学会 認定医
かみ合わせ認定医
厚生労働省認定研修指導医
歯学博士