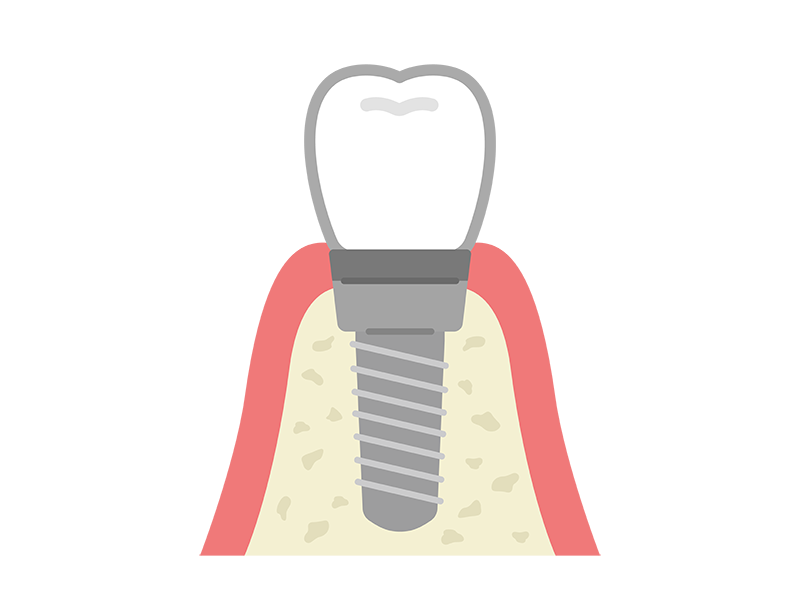こんにちは、学芸大学の歯医者、碑文谷さくら通り歯科 院長の太田です。
私たちは、毎日何気なくものを食べています。
その動作は、
『食べ物を口に入れ、唾液を出しながら、舌を上手に動かして食べ物を歯に移動させ、歯でかみ砕いたり、すりつぶしたりして、十分に食べ物が細かくなったら、の奥に送り込んで呑み込む』
ということになります。
このような複雑なことを大して意識せずにやっていて、この食べ物を食べる、口から胃に食べ物を運ぶ(噛むことと呑み込むこと)という一連の動作のことを嚥下(えんげ)と呼びます。
たまにむし歯が痛んだり、口内炎ができたり、カゼで喉が腫れたりすると、それだけで、この一連の作業はうまく回らなくなり、不自由な思いをするだけでなく、おいしい料理もおいしく感じないし、食べる気も萎えてきたりします。
何気なくやっていることですが、うまく出来なくなったときにその大切さに気付きます。
これらは「嚥下障害」と呼ばれます。

一時的な痛みや腫れであれは、それが治れば嚥下障害も解決するのですが、嚥下に必要な「噛む力」と「呑み込む力」は年齢とともに衰えてきます。
加齢による下力の衰えは急に来るものではなく、その徴候もイ々に増えてきます。
例えば、以下のようなことが、気になるほど起こるようであれば、注意が必要です。
・食べるスピードが遅くなる、食べる量が減る
・いつの間にかよだれが出ている
・よくむせる
・食べ物をこぼす
・痰が絡みやすい
・声がかすれる
嚥下力が落ちてきて、うまく働かなくなると唾液や食べ物、胃の逆流物などが誤って、気管に入ってしまうことがあり、誤嚥(ごえん)といいます。
気管に入った唾液や食べ物に含まれる細菌が肺に送り込まれると、なかで炎症を起こすことがあり、咳
き込んだり高熱が出たりします。
これが誤嚥性肺炎で、日本人の死因のなかで5番目に多い肺炎のなかで、その原因の7~8割を占めると言われています。
嚥下力を保つこと=噛む力と呑み込む力を保つことは、私たちの生活を快適にするために欠かせません。
碑文谷さくら通り歯科
院長 太田彰人
日本歯周病学会 認定医
かみ合わせ認定医
厚生労働省認定研修指導医
歯学博士