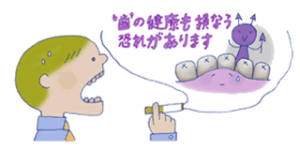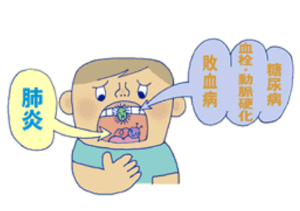こんにちは、学芸大学の歯医者「碑文谷さくら通り歯科」です。
「マウスピース矯正って本当に効果あるの?」「痛くないって聞くけど本当?」そんな疑問を抱えていませんか?
当院でも近年マウスピース矯正(インビザラインなど)を希望される方が急増していますが、治療を始める前に知っておくべきことを理解しておかないと、思っていた結果と違って後悔することもあります。
今回は、マウスピース矯正を検討している方へ向けて、後悔しないために知っておいてほしい「5つのポイント」を詳しく解説します。
目次
- 1. すべての歯並びに適しているわけではない
- 2. 装着時間の自己管理が治療結果を左右する
- 3. 食事・歯磨き・衛生面の習慣が変わる
- 4. 歯科医院選びで治療の質が大きく変わる
- 5. 見た目だけでなく「かみ合わせ」まで考えることが大切
1. すべての歯並びに適しているわけではない
マウスピース矯正は、透明で目立ちにくく、取り外しも可能なため人気の高い矯正法ですが、実はすべての歯並びに適しているわけではありません。
軽度から中等度の歯並びの乱れに対しては高い効果を発揮しますが、以下のようなケースでは向かないことがあります:
- 上下の顎の位置にズレがある(骨格的な不正咬合)
- 奥歯のかみ合わせを大きく動かす必要がある
- 重度のねじれや回転を伴う歯並び
「マウスピース矯正を選んだものの、やっぱりワイヤーに変更せざるを得なかった…」という声も少なくありません。
当院では、精密検査と3Dシミュレーションを活用して、最初の時点で適応かどうかを見極め、患者様にとってベストな選択をご提案しています。
2. 装着時間の自己管理が治療結果を左右する
マウスピース矯正の最大の特徴であり、難しさでもあるのが「装着時間の自己管理」です。
マウスピースは1日20時間以上の装着が必要とされていますが、「装着を忘れた日が続いた」「旅行先で外していたら合わなくなった」という事例も多く報告されています。
実際に、当院に相談に来られた方の中にも、他院で治療中に「自己管理ができずズレてしまった」「結局再作成になって費用がかかった」というケースがありました。
3. 食事・歯磨き・衛生面の習慣が変わる
マウスピース矯正は、食事や歯磨きの習慣に大きな変化をもたらします。基本的に、食事のたびにマウスピースを外し、食後は歯磨きをしてから再装着する必要があります。
このルールを守らないと、虫歯や歯周病のリスクが格段に上がってしまいます。糖分の多い飲料を飲んだままマウスピースを装着すると、プラークが密閉され、虫歯の温床になることも。
また、間食が多い方や外食が多い方は、「いちいち外すのが面倒」と感じて装着時間が減ってしまう傾向もあるため、事前に生活リズムの見直しが必要です。
慣れるまでは手間に感じるかもしれませんが、多くの患者さまが1〜2週間で習慣化できています。特に10代・20代の方よりも、自己管理が得意な30代以降の方に好まれる傾向があります。
4. 歯科医院選びで治療の質が大きく変わる
マウスピース矯正は「どこで受けるか」によって結果が大きく変わります。
安価な矯正プランを掲げるチェーン型の矯正サービスなども増えていますが、実際には歯の動きの細かなコントロールや、治療中のトラブル対応が不十分なこともあります。
当院では、矯正ページにも記載しているとおり、矯正認定医が診断から完了まで責任をもってサポートしています。
さらに、かみ合わせや咬合バランスのチェックも行い、「見た目はキレイだけど噛めない」という事態を防ぐ体制を整えています。
長期的な安心のためには、費用だけでなく「どんな診療体制か」「相談しやすいか」も含めて医院選びを行いましょう。

5. 見た目だけでなく「かみ合わせ」まで考えることが大切
「歯並びを整える=見た目の美しさ」と思われがちですが、矯正治療は本来「噛み合わせを整えて、将来の健康を守ること」が大きな目的です。
噛み合わせが悪いまま歯を整えてしまうと、以下のような問題が起こるリスクがあります:
- 顎関節症(口が開きにくい・音が鳴る・痛み)
- 咬合性外傷による歯のグラつきや欠損
- 偏った咀嚼による肩こり・頭痛・姿勢不良
矯正後に「前より噛めなくなった」という声を耳にすることもありますが、これは“見た目だけ”にとらわれてしまった結果です。
当院では、かみ合わせ治療にも力を入れ、治療前後の咬合バランスの確認を徹底しています。見た目と健康の両立を目指す方は、ぜひご相談ください。
まとめ
マウスピース矯正は、非常に魅力的な治療法ですが、その成功には「正しい理解」と「継続する努力」、そして「適切なサポート」が不可欠です。
「何となく周りがやっているから」「目立たなそうだから」という理由だけで始めてしまうと、後悔につながることもあります。
当院では、治療開始前に無料カウンセリングを実施し、患者様のライフスタイル・希望・歯並びの状態を総合的に評価したうえで、最適なプランをご提案しています。
ご不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
碑文谷さくら通り歯科
院長 太田 彰人
日本歯周病学会 認定医
日本顎咬合学会 認定医
かみ合わせ認定医
厚生労働省認定研修指導医
歯学博士