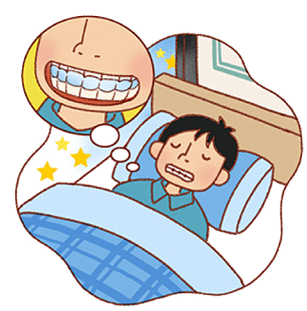「歯がしみる」「詰め物がとれた」その時どうする?学芸大学の歯医者が解説
こんにちは、学芸大学の歯医者 碑文谷さくら通り歯科 院長の太田です。
歯科医師になって26年、これまで数多くの患者様と向き合ってきました。今回は、「歯がしみる」「詰め物が取れた」など、よくあるトラブルが起きたとき、どのように対処すべきかを解説していきます。
概要
突然の歯のトラブルは不安や焦りを感じるものです。「冷たいものがしみる」「奥歯の詰め物が外れた」そんなとき、応急処置として何をすればいいのか、歯科医院を受診するタイミングはいつがよいのか。この記事では、よくある2つの症状について原因や対策を詳しく解説します。
目次
歯がしみる原因とは?
「冷たい水を飲むとキーンとしみる」「風が当たると痛い」…このような症状は知覚過敏である可能性があります。知覚過敏は、歯の表面のエナメル質がすり減ったり、歯ぐきが下がって象牙質が露出したりすることで起こります。
ただし、しみる症状の裏には虫歯や歯周病、詰め物の不適合など、他の病気が隠れていることもあるため注意が必要です。
▶詳しくはこちら:予防歯科でできること
詰め物がとれたときの対処法
食事中や歯磨きの際に「ガリッ」と異物感を感じたら、それは詰め物や被せ物が外れたサインかもしれません。
このような場合、以下の点に注意してください:
- とれた詰め物は捨てずに清潔な容器に保管する
- とれた部分で硬いものを噛まない
- できるだけ早く歯科を受診する
無理に戻そうとしたり、市販の接着剤でつけ直したりするのは危険です。かえって症状を悪化させることがあります。
応急処置はどうすればいい?
自宅でできる応急処置は限られていますが、以下のような点に気を付けると安心です。
- 痛みがある場合:市販の鎮痛剤(アセトアミノフェンなど)を服用
- しみる場合:冷たい飲食物を避け、常温の水や食事を心がける
- 詰め物がとれた場合:とれた場所を避けて食事する
応急処置はあくまで「一時的な対応」です。違和感や痛みが続く場合は早めの受診が必要です。

歯科医院に行くべきタイミング
以下のような場合は、できるだけ早めに歯科医院を受診しましょう:
- しみる症状が1週間以上続く
- 詰め物がとれてから数日以内に痛みが出てきた
- 歯に穴が空いている感覚がある
初期段階での治療であれば、比較的簡単な処置ですむことが多く、痛みや費用も少なくて済みます。
当院でも、「詰め物がとれたけど放置してたら痛みがひどくなった」「我慢できずに夜間救急に行った」というケースを多く見ています。
▶診療案内はこちら:アクセス・診療時間
まとめ:自己判断せず早めの受診を
「歯がしみる」「詰め物がとれた」という症状は、放置することでより大きな問題に発展することがあります。
自己判断で処置をすると、かえって症状を悪化させたり、治療が長引いたりすることもあります。
少しでも違和感を感じたら、お気軽に歯科医院にご相談ください。
当院では、急患対応も行っておりますので、お困りの際はまずお電話ください。
学芸大学駅から徒歩圏内、土日も診療の碑文谷さくら通り歯科が皆様の健康をサポートします。
碑文谷さくら通り歯科
院長 太田 彰人
日本歯周病学会 認定医
日本顎咬合学会 認定医
かみ合わせ認定医
厚生労働省認定研修指導医
歯学博士